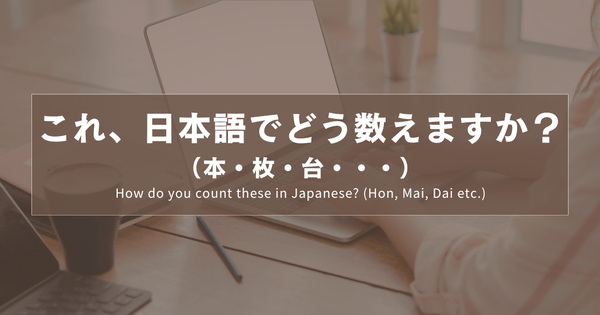こんにちは、さゆりです。みなさん、お元気ですか。
みなさんは今学生ですか。それとも仕事をしていますか。仕事をしている方だったら、1日何時間仕事をしますか。日本では最近「働き方改革」という言葉をよく聞きます。働き方改革(はたらきかたかいかく)とは、働く人々の仕事のやり方を改善し、より良い環境を作るための取り組みです。日本では、長時間働くことが問題になっているため、働く時間を減らしたり、柔軟な働き方を推進したりしています。例えば、テレワークやフレックスタイムなど、仕事の時間や場所を自由に選べるようにすることが改革の一部です。目的は、仕事と生活のバランスを取ること、そして働きやすい環境を作ることです。
今回はこの「働き方改革」の中でも教員の働き方に関するニュースを話します。教員は学校で教える仕事をしている人のことを言います。世界各国で教員の勤務時間や働き方が注目されていますが、日本の教員は特に長い時間働いていることが、OECD(経済協力開発機構)の調査で分かりました。どんな結果だったか、ニュースを聞いてみましょう。
「OECDは、世界各国の教員を対象に勤務実態や指導内容を調べるため、約5年に一度のペースで調査を行っています。昨年行われた調査には、世界55の国と地域から約7000人の教員が参加し、日本の小中学校の教員も参加しました。
その結果、日本の小中学校の教員が最も長い時間働いていることが分かりました。日本の小学校の教員は、1週間の勤務時間が平均52.1時間で、これは世界平均の40.4時間よりもかなり長い時間です。中学校の教員は、さらに長く、1週間の勤務時間は平均55.1時間でした。これは、世界の平均を14時間ほど上回っています。
文部科学省は、日本の教員は授業以外にも多くの役割を担っており、これが長時間労働の原因だと考えています。そして、教員の役割を見直し、改善を進める必要があるとしています。」
みなさん、よく分かりましたか。今回は日本の小中学校の先生が世界で一番長く働いているというニュースでした。それでは、内容をもう一度いっしょに確認しましょう。
OECD(経済協力開発機構)は世界各国、世界のいろいろな国々の教員を対象に調査をしました。この調査で、日本の小中学校の教員が最も長い時間働いていることが分かりました。小学校の教員の1週間の勤務時間は平均52.1時間でした。勤務時間、この言葉を聞いたことがありますか。勤務時間は、仕事をしている時間、働く時間のことです。この勤務時間は世界の平均よりも長い時間でした。中学校の教員は、小学校の教員よりもさらに長く勤務時間の平均は55.1時間でした。これは世界の平均を14時間ほど上回っています。上回るとは、ある基準や数字、予想などを超えること、それより多いことです。
そして、文部科学省は、日本の教員は授業以外にも多くの役割を担っており、これが長時間労働の原因だと考えていると話しました。文部科学省は日本の政府機関の一つで、教育や文化、科学、スポーツなどの仕事を担当しています。日本の教員は授業以外にも多くの役割を担っています。役割というのは、なにかの仕事や責任のことで、特定の人や物がするべき役目を指します。担うというのは自分が責任を持って行うこと、重要な役割や仕事を引き受けるという意味です。そして、この仕事を見直し、改善を進める必要があると話しました。改善は、問題を解決して、よりよくすることです。
それではニュースをもう一度聞いてみましょう。
「OECDは、世界各国の教員を対象に勤務実態や指導内容を調べるため、約5年に一度のペースで調査を行っています。昨年行われた調査には、世界55の国と地域から約7000人の教員が参加し、日本の小中学校の教員も参加しました。
その結果、日本の小中学校の教員が最も長い時間働いていることが分かりました。日本の小学校の教員は、1週間の勤務時間が平均52.1時間で、これは世界平均の40.4時間よりもかなり長い時間です。中学校の教員は、さらに長く、1週間の勤務時間は平均55.1時間でした。これは、世界の平均を14時間ほど上回っています。
文部科学省は、日本の教員は授業以外にも多くの役割を担っており、これが長時間労働の原因だと考えています。そして、教員の役割を見直し、改善を進める必要があるとしています。」
2回目は、1回目よりもよく分かりましたか。
それでは、なぜ日本の教員がこんなに長時間働いているのかを少し考えてみましょう。
日本の教員は、授業だけではなく、生徒指導や部活動、それに書類作成などの仕事も担当しています。生徒指導というのは学生が学校で、学習や生活をうまく送れるように助けること、そして部活動は学校で行うクラブ活動のことです。特に部活動は、1週間の勤務時間に大きな影響を与えていて、これが日本の教員が長時間働く原因の一つです。日本は先生が、部活動、クラブ活動の指導もしていることが多いですが、みなさんの国はどうですか。
また、最近の調査結果では、学校の校長の40.7%が「教員の不足を感じている」と回答しているようで、教員不足も大きな問題となっています。不足というのは、十分じゃない、足りていないという意味です。なので、早く先生たちが働きやすい環境を作って、教員数を増やさないといけません。
それでは、最後に今回紹介した言葉をもう一度確認しましょう。
教員 – 学校で教える仕事をしている人。
勤務時間 – 仕事をしている時間。
上回る – ある基準や数字、予想などを超えること、それより多いこと。
文部科学省 – 日本の政府機関の一つで、教育や文化、科学、スポーツなどの仕事を担当している。
役割 – なにかの仕事や責任のことで、特定の人や物がするべき役目を指す。
担う – 自分が責任を持って行うこと、重要な役割や仕事を引き受けるという意味。
改善 – 問題を解決して、よりよくすること。
部活動 – 学校で行うクラブ活動。
教員不足 – 教員が足りない状態。
今日は日本の小中学校の教員の労働時間が世界で一番長いというニュースを紹介しました。
教員の仕事は授業だけじゃなくて、いろいろな役割があるので長時間仕事をしていることが分かりましたね。そして今日本は教員不足、教員の数が足りていないということも紹介しました。みなさんの国はどうですか。ぜひコメント欄で教えてくださいね。そして、みなさんがポッドキャストで聞きたいテーマがあれば、それもぜひコメント欄で教えてください。それでは、今回はここで終わります。また次のポッドキャストでお会いしましょう!