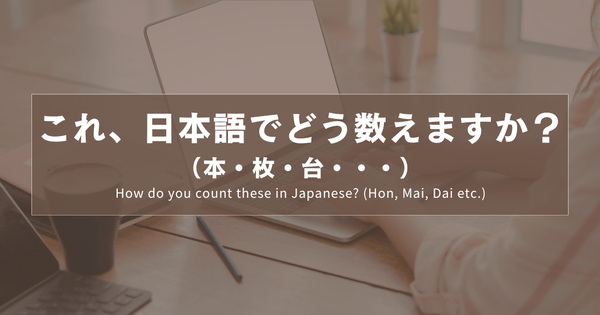こんにちは、さゆりです。みなさんお元気ですか。
もう7月になりましたね。今私は7月6日にこのポッドキャストの録音をしています。最近日本で街を歩くといろいろなところで七夕の飾りを見ることができます。7月7日は「七夕」の日だからです。ショッピングモールや駅など、いろいろなところで見られますよ。みなさんはこの七夕飾りを見たことがありますか。そして、みなさんはこの「七夕」についてよく知っていますか。今日はこの「七夕」の由来や、日本では7月7日の七夕の日に何をするのか紹介しようと思います。
[日常]7月7日は何の日?
七夕の由来や日本の習慣について紹介。短冊に願いを書いたり、飾りを作ったりする伝統的な過ごし方や、七夕の日に食べる食べ物を紹介します。
![[日常]7月7日は何の日?](https://images.unsplash.com/photo-1688822483660-5ad864b0ded8?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=M3wxMTc3M3wwfDF8c2VhcmNofDJ8fCVFNCVCOCU4MyVFNSVBNCU5NXxlbnwwfHx8fDE3NTE4MDI3NDd8MA&ixlib=rb-4.1.0&q=80&w=1200)
始めに七夕の由来について話します。このポッドキャストはいろいろな国の方が聞いてくださっていますが、聞いてくださっている方の中にもこの七夕を祝う国もあると思います。七夕は元々中国から伝わった伝説と日本の行事が融合してできました。始めに昔から伝わる七夕の話を紹介します。
昔々、神様の娘の織姫と、若者の彦星がいました。織姫は機織りが上手で、彦星は牛のお世話をするのが上手でした。機織りというのは糸を使って布を作ることです。二人は、とても仲良しで、いつも一緒に遊んでいました。でも、二人は遊んでばかりで、仕事をしなくなってしまいました。それを知った神様は、怒って、織姫と彦星を天の川の両岸に離ればなれにしてしまいました。悲しんだ織姫と彦星は、毎日泣いてばかりいました。それを見て、神様は一年に一度だけ、7月7日に会うことを許してくれました。それ以来、織姫と彦星は、7月7日になると、天の川を渡って会うことができるようになりました。これが七夕のお話です。
つぎに、七夕の日に日本ではどんなことをするのか知っていますか?まず一番有名なのは、短冊に願い事を書いて竹に飾ることです。短冊というのは細長い紙です。願いを書いて飾ると、織姫と彦星の力で願いが叶えられたり、みんなを悪いものから守ってくれるという言い伝えがあるんだそうです。短冊に書く内容は、人それぞれです。先日駅に飾られている短冊を少し見たのですが、「試験に合格しますように」「健康に過ごせますように」「恋人とずっと仲良くいられますように」などいろいろなお願いが書いてありました。
また、七夕には「七夕飾り」を作る習慣もあります。紙で作った鶴や星などいろいろな飾りを竹に飾ります。これらの飾りは、それぞれ意味があります。例えば鶴の飾りは「長寿祈願」、長く生きられますようにという意味が込められています。星の飾りは、「願いが空高くまで届きますように」という意味があります。竹に色とりどりの短冊や飾りが付けられているのを見ると、とてもきれいですよ。みなさんも機会があったら、願いを書いたり、飾りを作ったりしてみてくださいね。
そして、七夕の日の夜、空を見上げると織姫の星「ベガ」と彦星の星「アルタイル」、そしてその間には「天の川」も見ることができます。なので、天気がよければ、空を見てみるのもいいですね。天の川を渡って、織姫と彦星が会っているのかなと考えると、とてもロマンチックですね。
七夕によく食べられる食べ物もあります。これは地域や人によっても違うのですが、有名なのが「そうめん」です。そうめんは白くて、細い麺です。そうめんを食べるようになった由来はいろいろな説があるようなのですが、健康を祈って食べるという説や、細くて長い麺を天の川や織姫の織り糸に見立てているという説もあります。他にもちらし寿司や、星をモチーフにした食べ物もよく食べられます。
今日は日本での七夕の過ごし方についてお話ししました。みなさんは短冊に願いごとを書くなら、どんなことを書きますか。私は「心も体も健康に、毎日楽しく過ごせますように」と書きたいと思います。あと私は中国語の勉強もしているので、「中国語が上達しますように」と書いてもいいかもしれません。それからみなさんは今日本語の勉強をしていますか。私は、今オンラインで日本語のレッスンをしています。レッスンに興味がある方は概要欄にメールアドレスがあるので、メッセージをくださいね。そして、ポッドキャストのスクリプトが見たい方も概要欄にURLがあるので、そこから見てみてください。それでは、また次のポッドキャストでお会いしましょう。